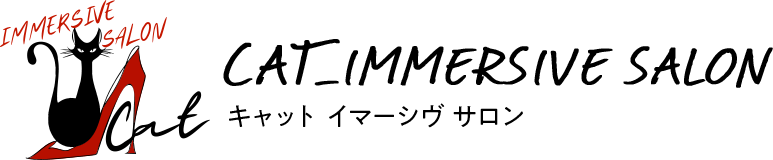Diary 写メ日記の詳細

こんにちは。
CATの羽田千冬(はねだ ちふゆ)でございます。
本日は人体の不思議発見キャス直前のため、
「身体」について、
少しお話しさせていただきます。
皆様は身体のどこかを
つったことはありますか?
おそらく、あると答える方が大半でしょう。
つる原理を知らなかったので、
AIに聞いてみました、出力結果は以下です。
ーーーーー
主な原理・メカニズム
• 神経と筋肉の伝達システムの乱れ
筋肉は、脳からの「縮め」や「緩め」といった指令を受けて動いています。この指令は神経を通して筋肉に伝えられますが、何らかの原因でこの伝達システムに異常が生じると、筋肉が過剰に収縮してしまうと考えられています。
筋肉には、伸びすぎや縮みすぎを防ぐためのセンサー(筋紡錘、腱紡錘)がありますが、これらのセンサーの誤作動も痙攣の一因とされています。
つる原因となる主な要因
• 電解質(ミネラル)の不足
筋肉の収縮や神経の伝達には、カリウム、マグネシウム、カルシウム、ナトリウムなどの電解質が重要な役割を果たしています。汗を大量にかいたり、脱水状態になったりすると、これらのミネラルバランスが崩れ、筋肉が正常に機能しなくなって痙攣が起こりやすくなります。
• 水分不足・脱水
脱水状態になると、血液中の水分量が減少し、ミネラル濃度が変化します。また、筋肉への血液供給が不十分になり、酸素や栄養が行き届かなくなるため、筋肉が正常に収縮・弛緩できなくなります。
• 筋肉の疲労
激しい運動や長時間の同じ姿勢などによって筋肉が疲労すると、乳酸などの疲労物質が蓄積します。これにより、筋肉の収縮をコントロールする機能がうまく働かなくなり、痙攣を誘発しやすくなります。
• 冷え・血行不良
体が冷えると、筋肉や血管が収縮して血行が悪くなります。血行不良は、筋肉への酸素や栄養の供給を妨げ、老廃物の排出も滞らせるため、筋肉の機能が低下してつりやすくなります。
• 加齢
加齢に伴い、筋肉量が減少し、神経や筋肉の機能も衰えます。また、脱水や冷えなど、つる原因となる様々な要因が重なりやすくなるため、高齢になるほどつりやすくなります。
• 病気や薬の影響
糖尿病、腎臓病、肝臓病、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアなどの病気や、特定の薬の副作用として、足がつりやすくなることがあります。
これらの要因が単独ではなく、複合的に作用して「つる」現象が起こると考えられています。特に、就寝中は発汗による脱水や体温の低下が起こりやすいため、足がつりやすいとされています。
ーーーーー
という感じです。
まだ完全に解明はされていないんだとか。
ここで、少し羽田の昔話を一つ。
羽田は高校時代、男子バレーボール部所属。
その部活は「スパルタ部活」と呼ばれる
根性論で成り立っている部活でした。
陸上部よりも走り、
バスケ部よりも飛ぶ。
この動作をひたすらやっていたわけで。
ある日の練習中。
強打レシーブをする時に
我々はステップを踏むのですが、
ステップを踏んで、
リズムを合わせた瞬間
両足同時につるという悲劇。
その時は立っていられないし、
痛過ぎて膝も曲がらなかったので、
周りからは一時期、
「V字開脚」と呼ばれました。
あの日の醜態は。
2度と忘れないぞ。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次にお会いできる日を楽しみにしています。
CATの羽田千冬でした。